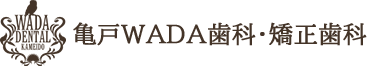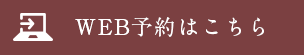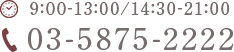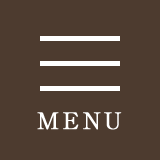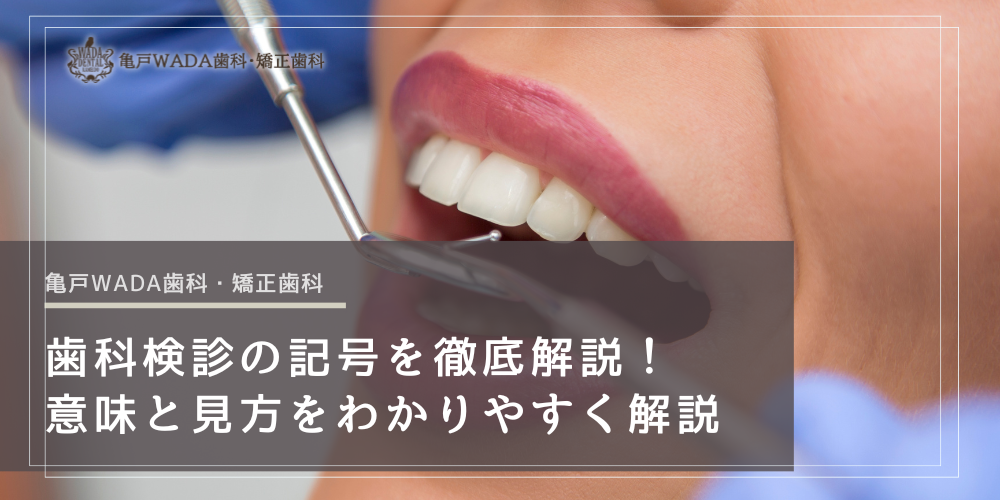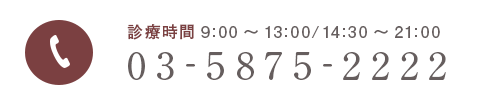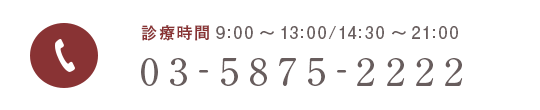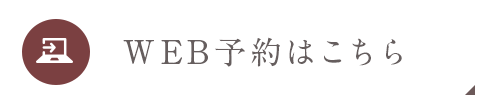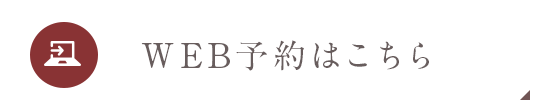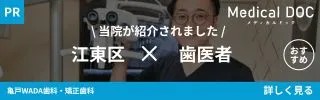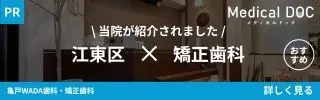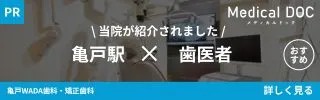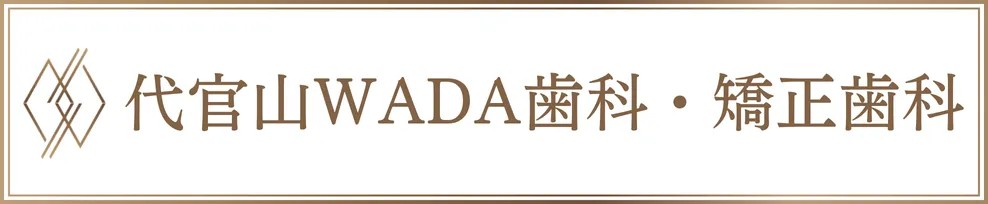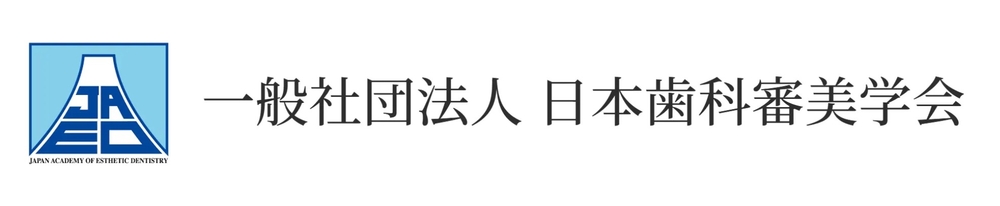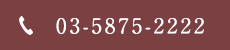虫歯になりやすい体質とは?原因と対策を徹底解説
2025.04.19更新

亀戸WADA歯科・矯正歯科です。
「毎日きちんと歯磨きしているのに、なぜか虫歯になりやすい」と感じていませんか?
その原因は、実は体質や生活習慣にあるかもしれません。
虫歯になりやすい人の特徴と予防法について解説します。
今回は、虫歯ができる仕組みや体質との関係、日常生活で気をつけるポイントをわかりやすくご紹介します。
「虫歯になりにくい口」を目指すために、今日から実践できる対策も多数掲載しています。
結論として、体質だけでなく習慣を見直すことで虫歯は予防できるのです。
虫歯になりやすい人の特徴とは
虫歯になりやすい体質の人には、共通するいくつかの特徴があります。
まず、歯質が弱かったり歯並びが悪いと、虫歯菌の攻撃に耐えられず虫歯ができやすくなります。
また、唾液の量が少ないと口腔内の自浄作用が低下し、虫歯菌が繁殖しやすくなります。
さらに、間食が多い・甘いものを好むといった食習慣も虫歯のリスクを高める要因です。
これらの要素は複数重なることで、虫歯の発生確率が一気に高まります。
体質だからとあきらめず、生活習慣の改善で予防が可能です。
虫歯ができる仕組みを理解しよう
虫歯は「ミュータンス菌」に代表される虫歯菌が、糖分を分解して酸を出し、歯を溶かすことで発生します。
つまり、口の中に糖が長く残っている状態が続くと、酸性環境が保たれ歯が溶けやすくなります。
また、歯垢(プラーク)に多くの菌が潜み、その中で活性化することで虫歯が進行していきます。
歯質が酸に弱い人や、唾液が少なく中和作用が十分でない人は、特に虫歯リスクが高くなります。
虫歯は細菌・歯質・糖分・時間という4つの要素が重なることで進行することを理解しましょう。
虫歯になりやすい生活習慣を見直す
虫歯のリスクを減らすには、日常の習慣を見直すことが重要です。
特に食生活の影響は大きく、ダラダラと間食を続けたり甘いものを頻繁に摂ることで、虫歯菌にとって都合の良い環境が長時間続きます。
さらに、歯磨きの頻度や方法が不十分な場合、磨き残しが原因で虫歯菌が増殖します。
以下のような習慣は虫歯を招きやすいため注意が必要です。
- ・間食が多く、口の中が酸性になりやすい
- ・食後に歯磨きをしない
- ・夜食後にそのまま寝てしまう
- ・ジュースや砂糖入り飲料を頻繁に飲む
一つでも当てはまるなら、すぐに生活習慣を見直すことが大切です。
遺伝と虫歯体質の関係
虫歯になりやすい体質には遺伝も関係すると言われています。
特にエナメル質の強さや唾液の分泌量、歯並びなどは遺伝的要素の影響を受けます。
例えば、エナメル質が薄くて酸に弱い場合、同じ食生活でも虫歯ができやすくなります。
また、歯並びが悪いと歯磨きが不十分になり、磨き残しから虫歯が発生しやすくなります。
ただし、虫歯菌は生まれつき存在するものではなく、外部からの感染によって口腔内に定着します。
親子間での生活習慣が似ていることも、虫歯のリスクに影響を与えるのです。
虫歯になりにくくするための実践ポイント
体質だけでなく、日々のセルフケアが虫歯予防には不可欠です。
まず、食生活では甘いものや間食の回数を減らし、食事と食事の間隔をしっかり空けるようにしましょう。
さらに、以下のケアを取り入れることで口腔内環境を整えることができます。
- ・フッ素入り歯磨き粉を使用する
- ・歯ブラシだけでなくフロスや歯間ブラシを併用する
- ・毎食後の歯磨きを習慣化する
- ・定期的に歯科検診を受ける
- ・唾液分泌を促すためによく噛んで食べる
これらを実践することで、虫歯になりにくい口腔環境をつくることができます。
まとめ
虫歯になりやすい体質には、遺伝や唾液量、歯の質などが関係していますが、日々の生活習慣によって大きく左右されます。
甘いものや間食の摂り方、歯磨きの方法、歯科検診の頻度などを見直すことで、虫歯を防ぐことが十分可能です。
体質を理由にあきらめるのではなく、予防習慣を身につけることで健康な歯を保ちましょう。
正しい知識とケアを続けることが、虫歯を遠ざける第一歩です。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
江東区亀戸駅から徒歩5分の歯医者・歯科
TEL:03-5875-2222