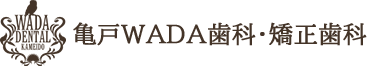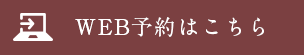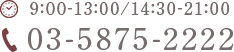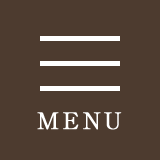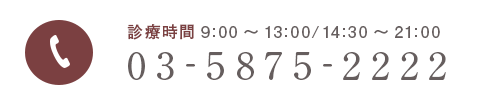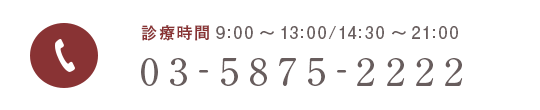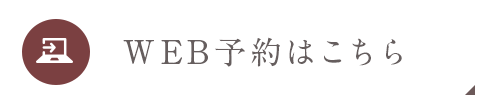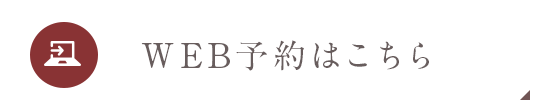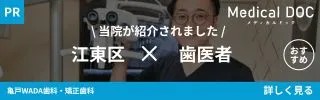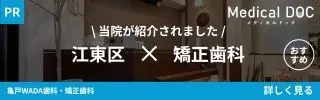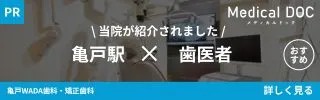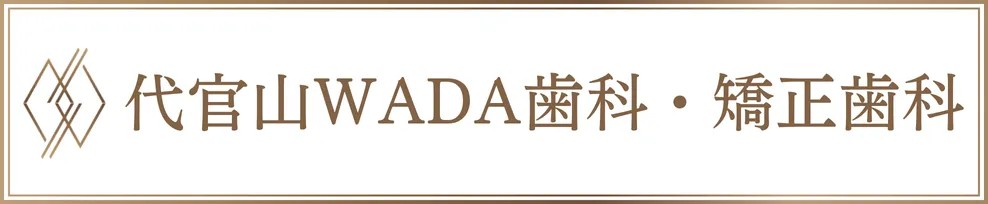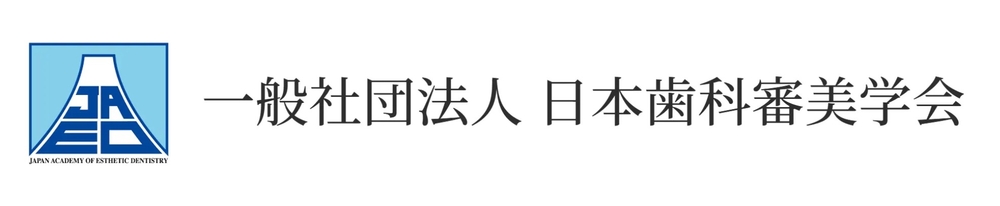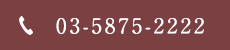顎関節症(あごの痛み・カクカク音)の原因と治療選択|自宅で悪化させないポイント
2026.01.20更新

「朝起きると顎がだるい」「食事のたびに耳のあたりでカクカク音がする」「大きなあくびをしたら口が閉じなくなった」
このような症状に悩まされていませんか?
顎(あご)の関節や、その周りの筋肉に異常が現れる「顎関節症」。かつては若い女性に多いと言われていましたが、近年ではパソコンやスマートフォンの長時間使用、ストレス社会を背景に、性別や年齢を問わず患者様が増えています。
顎の痛みは、単なる不快感だけでなく、「食事が楽しめない」「会話が億劫になる」といった生活の質(QOL)の低下に直結します。また、放置することで肩こりや頭痛、さらには歯そのものを破壊してしまうリスクも孕んでいます。
「いつか治るだろう」と痛みを我慢せず、まずはご自身の顎の状態を正しく理解することから始めましょう。
本記事では、顎関節症の正体と、私たち歯科医師がどのように診断し、治療を進めていくのか、そしてご自宅で気をつけていただきたいポイントについて、丁寧に解説していきます。
目次
1. その症状、本当に顎関節症? 3つの代表的なサイン
顎関節症は、単一の病気ではなく、顎の関節や筋肉に生じる様々な症状の総称です。国際的な基準や日本顎関節学会の分類など専門的な定義はありますが、患者様ご自身でチェックしていただきたい主な症状は以下の3つです。
- ① 顎が痛む(顎関節痛・咀嚼筋痛) 口を開け閉めする時や、食べ物を噛む時に、耳の前あたり(顎関節)や頬、こめかみ(咀嚼筋)に痛みを感じます。虫歯の痛みとは異なり、「筋肉痛」のような鈍い痛みや、関節の奥が響くような痛みが特徴です。
- ② 口が大きく開かない(開口障害) 正常な状態であれば、ご自身の指を縦にして3本分(約40mm以上)は口に入ります。しかし、痛みがあったり、関節の構造が引っかかったりして、指が1〜2本程度しか入らない状態を開口障害と呼びます。無理に開けようとすると強い痛みが走ります。
- ③ 顎を動かすと音がする(関節雑音) 口を開ける時に「カクッ」「コキッ」という音(クリック音)がしたり、「ジャリジャリ」「ミシミシ」という音(クレピタス音)がしたりします。これは、顎の関節の中にある「関節円板(クッションの役割をする組織)」がズレていたり、骨同士が擦れ合ったりすることで生じます。
これらの症状が一つでも当てはまり、一週間以上続く場合は、顎関節症の疑いがあります。
2. 歯科医が注目する「原因」は一つではない
「なぜ私が顎関節症に?」と疑問に思われる方も多いでしょう。昔は「噛み合わせの悪さ」が主原因と考えられていましたが、現在の歯科医学では、複数の要因が積み重なって発症する「多因子説」が定説です。私たちは以下の要素を複合的に診査します。
2-1. 噛み合わせと顎の位置のズレ
詰め物や被せ物の高さが合っていなかったり、抜けた歯を放置して歯並びが崩れたりすると、顎が本来の正しい位置で噛めなくなります。無理な位置で噛み続けることで、関節や筋肉に過剰な負担がかかり、炎症を引き起こすことがあります。
2-2. 無意識の癖「TCH(歯列接触癖)」の関与
これは非常に重要なポイントです。本来、人間の上下の歯は、食事や会話の時以外は「離れている」のが正常です。接触している時間は、1日合わせてもわずか20分程度と言われています。
しかし、パソコン作業中や家事、考え事をしている時などに、無意識に上下の歯を接触させ続けてしまう癖を「TCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)」と呼びます。
弱い力であっても、長時間接触し続けることで筋肉は緊張し続け、顎関節への負担が蓄積されます。これが現代の顎関節症の大きな要因となっています。
2-3. ストレスと生活習慣の影響
精神的なストレスは、筋肉の緊張を高めるだけでなく、夜間の「歯ぎしり・食いしばり(ブラキシズム)」を増悪させます。睡眠中の歯ぎしりは、体重の数倍もの力が顎にかかると言われており、関節を破壊する強力な要因となります。
また、頬杖をつく、うつ伏せ寝をする、片方の歯だけで噛む(偏咀嚼)といった日常の癖も、顎のバランスを崩す原因です。
3. 当院での治療アプローチと選択肢
顎関節症の治療は、いきなり手術をしたり、歯を削ったりすることは稀です。まずは体に侵襲の少ない「保存的療法」から開始し、症状の改善を目指します。
3-1. スプリント療法(マウスピース)による負担軽減
最も一般的かつ効果的な治療法です。患者様の歯型に合わせて作成した専用のマウスピース(スプリント)を、主に就寝中に装着していただきます。
これにより、顎関節にかかる負担を分散させ、筋肉の緊張を和らげることができます。また、歯ぎしりによる歯のすり減りも防ぐことができます。当院では、症状に合わせて適切な硬さや厚みのスプリントを設計します。
3-2. 噛み合わせの調整と補綴(被せ物)治療
明らかに強く当たりすぎている詰め物がある場合や、被せ物が不適合で顎の位置がズレている場合は、微調整を行います。ただし、安易に歯を削ると元に戻せないため、慎重な診断が必要です。
全体的な噛み合わせの崩壊が原因の場合は、矯正治療やインプラント、精密な被せ物を用いて、顎が安定する噛み合わせを再構築する計画をご提案することもあります。
3-3. 薬物療法と理学療法
痛みが強く、口を開けるのも辛い急性期には、消炎鎮痛剤を使用してまずは炎症を抑えます。筋肉の痛みが強い場合は、筋弛緩薬を処方することもあります。
また、ご自身で行っていただくマッサージや開口訓練(リハビリ)も指導いたします。硬くなった筋肉をほぐし、関節の可動域を広げるために非常に有効です。
4. 自宅で悪化させない!今日からできるセルフケアとNG行動
顎関節症は「生活習慣病」の側面もあります。歯科医院での治療と並行して、ご自宅でのケアを行うことが早期改善への近道です。
4-1. 顎を安静にする「安静位」を覚える
先ほど触れたTCH(歯列接触癖)を改善しましょう。
「唇を閉じ、上下の歯は離し、顔の力は抜く」
これが顎にとっての安静な状態です。ふとした瞬間に歯が触れ合っていることに気づいたら、すぐに離して深呼吸をしてください。「歯を離す」と書いたメモを目につく場所に貼るのも有効な行動療法です。
4-2. 絶対に避けるべき「硬い食品」と「姿勢」
痛みが強い時期は、フランスパン、スルメ、ビーフジャーキーなどの硬い食品や、ガムのように長時間噛み続ける食品は避けてください。おかゆやうどんなど、あまり噛まなくてもよい食事を摂り、関節を休ませましょう。
また、頬杖や猫背(スマホ首)は、下顎を後ろに押し込み、関節を圧迫します。良い姿勢を保つことは、顎だけでなく全身の健康にも繋がります。
4-3. ホットパックによる血流改善
急激な痛みや熱感がある場合を除き、慢性的な痛みや凝りに対しては「温める」ことが有効です。蒸しタオルなどで顎の周りや首筋を温めると、血流が良くなり、蓄積した疲労物質が流れやすくなります。入浴時にゆっくり湯船に浸かるのも良いでしょう。
5. まとめ
顎関節症は、放置すると口が開かなくなるだけでなく、頭痛や肩こり、自律神経の乱れなど全身の不調に繋がることもある厄介な病気です。
しかし、適切な診断のもと、原因となっている習慣を見直し、必要なケアを行えば、多くの場合は手術などをせずとも症状をコントロールすることが可能です。
「たかが顎の音」と思わずに、違和感を感じたら早めにご相談ください。
亀戸WADA歯科・矯正歯科では、マイクロスコープやCTを用いた精密な診査診断を行い、お一人おひとりのライフスタイルに合わせた治療計画をご提案いたします。
亀戸で顎関節症や顎の痛み、噛み合わせの治療についてのご相談なら、亀戸WADA歯科・矯正歯科へお任せください。
皆様が痛みを気にせず、美味しく食事ができる毎日を取り戻せるよう、全力でサポートさせていただきます。